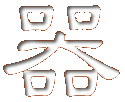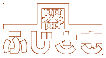やきもの見聞録
| このページでは、作家さんの工房を訪ねた時の事や、仕入れで訪問した街や店の様子、街で目にしたやきものや陶器、器などに関して、見たり聞いたりしたことを書いてゆきます。 ▼バックナンバー >>No21〜30 ▼バックナンバー >>No11〜20 ▼バックナンバー >>No1〜10 |
||
|
|
||
| ●2011/07/24 | 篠原 希さん 池袋東武での個展訪問 | |
| No36 |  去年も行きましたが、今年も信楽の若手作家さん 篠原 希(しのはらのぞむ)さんの個展が、東京池袋の東武百貨店であったので、見てきました。 去年も行きましたが、今年も信楽の若手作家さん 篠原 希(しのはらのぞむ)さんの個展が、東京池袋の東武百貨店であったので、見てきました。今回は穴窯の中でチンチンに焼けているところを、長い金の棒で引き出しす「引出し」という手法の作品がいくつかあり、青みのあるとてもきれいな焼き上がりの作品でした。 |
|
| ●2010/07/25 | 信楽焼 篠原 希さん 個展訪問 | |
| No36 |  信楽の若手作家 篠原 希(しのはらのぞむ)さんの個展が、東京池袋の東武百貨店であったので、見てきました。 信楽の若手作家 篠原 希(しのはらのぞむ)さんの個展が、東京池袋の東武百貨店であったので、見てきました。窖窯(あながま)での作陶で、焼締めで、灰の被り方もさまざまで、引出など、いろいろな表情の作品がたくさんあって、とても将来が楽しみな作家さんです。2010年の秋には、当店でも個展を開催していただく予定です。 |
|
| ●2006/03/12 | 青梅市 陶房吉田 訪問 | |
| No35 |  東京の郊外、青梅市にある「陶芸家吉田明」さんのお店。 東京の郊外、青梅市にある「陶芸家吉田明」さんのお店。工房は別の場所にあって、こちらはお店です。吉田さんの奥さんがお店を仕切っています。 先生の作品だけではなく、お弟子さんの作品も多数あって、どれもすごくレベルが高い、すばらしい作品ばかりでした。 |
|
| ●2005/06/26 | 朝霞市 かふぇぎゃらりー 八右衛門 訪問 | |
| No34 |  朝霞市の住宅街にある、れすとらんかふぇギャラリーの「八右衛門」さんに行ってきました。 朝霞市の住宅街にある、れすとらんかふぇギャラリーの「八右衛門」さんに行ってきました。当店のお客様でもあり栄養士の資格のある、オーナー手作りの料理とカフェ、そしていろいろな作家さんの作品を集めて販売もされています。 陶芸教室も併設されていいます。 |
|
| ●2005/06/19 | 福岡県 小鹿田焼 | |
| No33 |  福岡県日田市の北部にある源栄町皿山地区が小鹿田(おんた)焼きの里です。 福岡県日田市の北部にある源栄町皿山地区が小鹿田(おんた)焼きの里です。この小鹿田焼きは宝永2年(1705年)に小石原焼きの分れ窯として始まったようです。 そのため、小石原焼きや高取焼き の影響を受けており、茶碗や鉢、甕、壷などの日用雑器をつくり、近郊の農家などに販売していたようです。 初期の頃は数件の窯で始まったようですが、今では窯は10軒ほどに増えていますが、子供から孫、またその子供へと、一子相伝の流れで作られ、窯も共同の登り窯が使用されています。 それぞれの窯元の家には渓流の水を利用してのシーソー水車の唐臼(からうす)があり、、付近で採集した陶土を粉砕し、自分たちで水に溶かして粘土を作っています。 ◆シーソー水車動画(10M) >>こちら(AVIファイル) 技法は、小石原焼のようなとびカンナや、刷毛目ほとんどです。 このシーソー水車の音が街のあちこちで聞こえ、日本の音100選にも選ばれています。 |
|
| ●2005/06/19 | 上野焼 庚申窯 | |
| No32 |  千利休から直接教えを受けた豊前藩主・細川忠興候が1600年頃に、李朝の陶工「尊階」を招き、水質、釉油の採取に最も適した上野の地に窯を築いたのが始まりといわれています。 千利休から直接教えを受けた豊前藩主・細川忠興候が1600年頃に、李朝の陶工「尊階」を招き、水質、釉油の採取に最も適した上野の地に窯を築いたのが始まりといわれています。このように茶器が始まりで、九州地方の陶器としては特徴のある青緑の釉薬などを用いて、独特の大陸的な雰囲気があります。また、陶器でありながら肉厚の薄い、口当たりの良いのが特徴です。 |
|
| ●2005/06/19 | 小石原焼 泉利美窯 | |
| No31 |  小石原焼は福岡県と大分県の県境の近くにあります。 小石原焼は福岡県と大分県の県境の近くにあります。山の中の集落に4〜50軒ほどの窯元があります。歴史は江戸初期ぐらいからで、日常使いの雑器が主体です。特徴は半渇きの粘土成型された物を、ロクロで回転させ、その肌にゼンマイの板のようなはがねを当てて、粘土に飛び模様を付ける「とびカンナ」という手法と、同じくロクロで回転させておいて、そこに大きな刷毛に釉薬を付けて、チョンチョンと刷毛を当てて飛び飛びの刷毛目模様を付けます。 |
|